
うつ病について
このページはうつ病について記載します。躁うつ病については記載していません。
”うつ”と”うつ病”
うつ病も広く認知されるようになりました。
お仕事をされている方の中には、
適応障害かうつ病の診断がついて簡単に休職してしまう、と感じる方もいるかもしれません。
誰でも憂うつな気分にはなりますが、どこからがうつ病なの?という疑問もあると思います。
野村先生の本(野村総一郎 『名医が答える!うつ病 治療大全』 2022年 講談社)に、うつとうつ病について分かりやすく載っていましたので、何点か記載します。
(この本は一般の方にも読みやすいと思います)
うつ=気分、状態
一時的な心の状態で、いわば生理的な現象
うつ病=病気
持続性や重症度、経過などが含まれる。
とあります。
うつの説明は分かりやすいと思います。
うつ病の場合には、気分としてのうつだけでなく、睡眠障害、頭痛、食欲不振といった身体的な症状が現れます。期間も2週間以上とされています。
野村先生の本には以下の表も載っていました。
| うつ病 | うつ(状態) | |
| 強い(しばしば妄想的) | 程度 | 弱い(現実からズレない) |
| 大きく阻害される | 日常生活 | それほど阻害されない |
| よいことがあっても よくならない | 状況変化の影響 | よいことがあると 少しよくなる |
| 人と接するのをいやがる | 対人接触 | 人に頼りたがる |
| まったくやりたがらない | 仕事、趣味 | やっていたほうが 気が紛れる |
| はっきりしていない | きっかけ | はっきりしている |
| 理解できないことが多い | 周囲の了解 | 十分理解できる |
| 長く続く(2週間以上) | 持続 | 時間経過とともに薄れる |
| よく効く | 抗うつ薬 | 効かない |
| しばしば自殺に至る | 自殺 | 比較的まれ |
うつ病は症状も程度も様々なので、この表のとおりとはいきませんが、
”状況変化の影響” ”対人接触” ”きっかけ”の項目は、参考になる気がします。
”周囲の了解”というのは、
うつ病だと「~が悪くなったのは、自分が災難をもたらすから」などのように、一般的には理解しにくい考えになることがあります。
うつ病の分類・診断・服薬
非定型のうつ病

上記の野村先生の表は、本の中で明示されていませんが、
典型的なうつ病(メランコリー型)として作成されていると思います。
このようなうつ病ならば本人も周囲も分かりやすく、うつ病になったことを納得しやすいと思います。
典型的ではない「非定型」のうつ病という分類もあります。
「良いことに対しては気分がよくなる」「食欲は過食傾向で体重増加」「過眠」「ひどい倦怠感」「他人からの批判に過敏」といった特徴があります。
文字数が多くなってしまうので、厚生労働省のページのリンクを貼らせていただきます。
https://kokoro.mhlw.go.jp/about-depression/ad001/
また以前に「新型うつ」という言葉が流行った?気がします。
うつ病で会社を休んだ方が、
休み始めてすぐに旅行に行って楽しそうな姿をSNSに載せる…
見た方からすると、
本当にうつ病なの?病気で休んでいるの?
となると思います。
「新型うつ」も「現代型うつ」も正式な診断名ではありません。
こちらも厚生労働省の『こころの耳』のページに載っています。
https://kokoro.mhlw.go.jp/mental-health-pro-topics/mh-pro-topics002/
「ディスチミア親和型うつ病」や「未熟型うつ病」といった当事者には厳しい記載もあります。
この『こころの耳』のページにも書いてありますが、
このようなうつ病は、薬を飲む・休養するだけではなかなか良くなりません。
もし薬を飲んで休んで良くなっても、仕事など以前と同じ環境に復帰すると、同じ繰り返しになってしまいます。
原因による分類(内因・外因・心因)
古い考え方ですが精神疾患の世界では、原因によって内因・外因・心因という分類があります。
内因性は遺伝や素因(精神疾患のなりやすさ)が原因、
外因性は脳や身体の疾患、薬物の影響などが原因、
心因性は心理的ストレスが原因、という考え方です。
心因性は、リストラが原因でうつ病、などのように一般に理解できるきっかけがあります。
外因性は、甲状腺機能低下症が原因でうつ病の症状が出る、アルコールでうつ病の症状が出る、という状態です。
内因性は、うまく説明できないのですが、脳の神経伝達物質の変化が生じてうつ病、という状態です。
外因性の場合は、まずはその原因の治療が必要になります。
心因性の場合は、薬だけではなく、心理的ストレスへの対応が必要になります。
抗うつ薬が効果的なのは内因性のうつ病です。
一般的に典型的なうつ病は、内因・外因・心因の分類では、この内因性のうつ病ということになるのですが…。
ただ実際には、内因と心因を明確に区別することは難しいです。
うつ病になる方は、何らかの心理的なストレスがかかっていますし、心理的ストレスがきっかけでも長期間続けば神経伝達物質の変化はおきます。
カウンセラーが内因を説明できないのも、明確に区別しきれない現実があるからなのですが…
原因ではなく症状で診断
上記に内因・外因・心因について記載しましたが、この原因による分類は公式なものではありません。
公式にならない理由は、この分類ではうまくいかない部分があるからなのでしょう。
うつ病に限らず、精神疾患の難しいところは、癌や胃潰瘍や糖尿病や虫歯のように、目で見て分かったり、レントゲンに写ったり、数値で診断できないところです。
精神疾患でも脳画像を撮ったりするようになり、〇〇症は脳の△△が××の傾向がある、と分かってきていますが、
だからといって、
脳画像を撮ってみたら××だった。だから〇〇症である、と特定できるところまでは進んでいません。
ですので、現在(令和6年時点)は原因ではなく症状(抑うつ気分、眠れない、罪責感、死にたい等)で診断しています。
世界保健機関(WHO)が出している『ICD‐10(疾病及び関連保健問題の国際統計分類 第10版』(令和6年に30年ぶりに改訂版のICD‐11が出たそうです)や、
『DSM-5(精神疾患の分類と統計マニュアル 第5版)』に載っているうつ病の診断基準を見て、
抑うつ気分、興味・喜びの喪失、不眠、無価値観が当てはまる→うつ病
と診断することになります。
(AIが診断基準をあっという間に教えてくれます)
この症状で診断することの問題点はいくつかありますが、その一つに、
うつ病ではないのにうつ病の症状が出る、
ということがあります。
たとえば甲状腺機能低下症(橋本病の症状の一つ)、PMS(月経前症候群)でも、うつ病の症状は出ます。
この時にうつ病と思って、うつ病の薬だけ飲んでもうまくいきません。
また、うつ病の症状があってうつ病と診断をしたが、実は双極性障害(躁うつ病)で、抗うつ薬を飲んだら躁状態になってしまった、ということも現実にあります。
そのため医師は症状以外にも血液検査をしたり問診をしたりして、可能性を絞り込んでいって診断をしていくのですが、
医師は病院の家賃も機材費も人件費も稼ぐ必要があるので、一回の診察にかけられる時間は限られています。
限られた条件の中で診断がうまくできるかどうかは、(医師の先生に怒られそうですが)正直なところ医師の腕次第と言えるのではないでしょうか。
(診断を間違えると見当違いな治療をすることになるので、診断は大事です)
なお、これは余談ですが、DSM-5をパラパラめくっていると症状を文字だけで表現しているので、
「けっこう診断基準に当てはまってるな」
と思う方は珍しくありません。
自分は〇〇病かも、と思っても忘れられればDSMの笑い話ですむのですが、
個人でインターネットで診断基準を見て、
自分は〇〇病と思って心配したり不安になったり、実際に受診するということも起きてしまいます。
では〇〇病・症なのか?というと、そういう訳ではなく、
その症状により日常に支障をきたしているかどうか、
という視点が必要になります。
服薬について
うつ病の薬を検索すると代表的なSSRI(セロトニン再取り込み阻害薬)という単語が出てきますが、
さらに調べるとモノアミン仮説という言葉が見つかると思います。
うつ病は、
神経伝達物質のモノアミン(セロトニン、ノルアドレナリン、ドパミンなど)が不足すると発症する、
という仮説です。
日本では、このモノアミン仮説に基づいた薬が使えるのですが、うつ病に効果があることもあれば、あまり効果がないこともあります。
うつ病に限らずですが、精神疾患は原因が明らかになっていないので、明らかではない原因に基づいて作った薬がどの程度効くのか…
という苦しい話になってしまいます。
では実際にうつ病に処方される薬は何パーセントくらいの確率で有効なのか?という疑問がわきますが、
統計はどうにでもコントロールできてしまいます。
世の医師の先生方は、抗うつ薬は効く人には効くが、効かない人には効かない、と認識して(かといって他に出せる薬もなく)処方箋を発行しているようです。
(カウンセラーは医師ではないので、言い切ることはできませんが、これが現実のようです)
受診について
診断や投薬について否定的なことばかり書いているようですが、
カウンセラー(鈴木)としては医療機関を否定する気は全くありません。
むしろ、うつの症状が苦しい場合には一度受診していただきたいと思っています。
このページに、精神疾患の原因による分類(内因・外因・心因)について少し記載してしまいましたが、
このようなことは医師の先生方はもちろん分かった上で診察をされています。
身体の病気を含めて鑑別診断ができるのは医師だからこそですし、身体の治療は医師にしかできません。
薬も、目の前の患者さんに効きそうかどうかを考えて出しているでしょう。
抗うつ薬が効いて、そのまま良くなる方もいらっしゃいます。
また抗うつ薬で効果がみられない際に、磁気や電気で頭部を刺激するという治療もあります。医師だからこそできることです。
(カウンセラー(鈴木)は詳しく書けませんが、効果がある方も、ない方もいるようです)
また休職の診断書を書けるのも医師ですし、
医師という肩書自体が家族や職場の理解・協力を引き出す力をもっているでしょう。
もし受診するか迷われるのであれば、カウンセラー(鈴木)としては最初に受診いただきたいです。
(精神科・心療内科の敷居もだいぶ下がり利用者も増えて、予約が取りにくいかもしれませんが)
受診をされて医師が、
薬を出すほどではない(薬で改善する症状ではない)と言ったり、
通院(薬やTMS(経頭蓋磁気刺激治療))だけではなく心理的な支援があった方が良いと判断したり、
通院しても症状が改善に向かわない、
といった際にはカウンセリングを検討されて良いと思います。
うつ病のカウンセリング

うつ病の原因とカウンセリングの必要性
うつ病の原因が一つであれば診断の精度は高くなるでしょうし、効果的な薬も作りやすいでしょう。
ですが、精神疾患はいくつもの原因が積み重なって発症すると言われています。
このページに内因・外因・心因と記載していますが、
精神疾患になるかどうかは内因・外因・心因のかけ算、とイメージしていただくと分かりやすいと思います。
もともとのうつ病のなりやすさ(遺伝など)や考え方(このページの後に出てくる認知の偏りなど)と、ストレスのかかる環境(夫婦の不仲、長時間労働、職場の人間関係やノルマなど)があり、
そこにきっかけ(離婚、失職、挫折、病気、何かの失敗や悪化など)が加わって、
許容量を超えてうつ病になります。
薬は神経伝達物質には働きますが、考え方・環境・きっかけには働きかけてくれません。
(薬で症状が改善することで、うつ病の原因やきっかけを乗り越えられる方もいます。繰り返しになりますが、カウンセラーは服薬に反対したいわけではありません)
親子関係、夫婦関係、職場の人間関係、挫折、病気、喪失体験など、ストレスとなる環境やきっかけになるようなイベントは沢山あります。
うつ病は、
これらのことに今までのやり方では対応しきれなくなったと身体が教えてくれている、
と考えることもできるでしょう。
カウンセラーはうつ病ということは認識した上で、
うつ病にとらわれずに、相談者の考え方・日頃のコミニケーション、対応しきれなくなった悩み・テーマを扱いたいと思います。
認知行動療法
うつ病の治療を検索すれば認知行動療法が出てきます。
服薬と心理支援(認知行動療法)が両輪、と国も大きな病院も載せていると思います。
厚生労働省のページにも
うつ病の認知療法・認知行動療法マニュアルが載っています。
(不安症(不安障害)の認知療法・認知行動療法マニュアルも載っています)
この『患者さんのための資料』で必要にして十分だと思うので、PDFを貼ってしまいます。
(このPDFを見た方は、このページの後の部分は読まなくて良いと思います)
認知療法では、認知(ものごとの捉え方・考え方)を変容させることで、改善しようとします。
行動療法では、行動は学習したものと考えます。ですので、問題は誤った学習の結果なので学習しなおす、というやり方で行動に働きかけます。
(もともと、ねずみがレバーを押したら餌が出ることを学習することで行動を強化する、などが始まり)。
不登校や広場恐怖の方が、スモールステップで少しずつ慣れていきましょう、というのは行動療法の呼び方では暴露療法となります。
できるところからやってみて(暴露して)、少しずつ範囲を広げる(行動・体験して、大丈夫と学習しなおす)ということになります。
それぞれの足りない部分を補い認知行動療法となっています。
認知行動療法は令和6年時点の日本で、健康保険の適用になる唯一の心理療法です。
(医師、または医師と看護師が共同して、という条件なので心理職は対象外ですが…)
認知行動療法が特別扱い?なのは何故なのでしょうか。
カウンセラー(鈴木)の単なる推測ですが、
認知行動療法はトレーニングのような感じで、内容や回数があらかじめ決まっているので、実施者による差が出にくく、効果が予測しやすい?から保険適用にしやすいのだと思います。
認知の変容
認知行動療法では、出来事と感情は変えることが難しいので、出来事をどう考えて(認知)、どう行動するか、と検討して実行します。
そして、感情と状況はどうなったか、と振り返ります。
これを表にしたのがコラム表です。
(認知行動療法の用語で認知再構成法。心理業界は専門用語にすると凄そうですが、実際は大層なものではありません…)
枠の数で3コラム・5コラム・7コラムなどあります。
『患者さんのための資料』には以下の7コラムの表が載っています。
| 状況 | 会社で私を残して事務職のみんなが上司と食事会に行った |
| 気分 | イライラ(70%)、あせり(65%)、悲しい(80%) |
| 自動思考 (ホットな思考に○) (確信度% | ○自分は嫌われている。 (80%) 仲間はずれにされている。(80%) 自分は仕事が遅いだめな人間だ。(70%) |
| 根拠 | 食事会に行けず、残業していた。 仕事が進まない。 |
| 反証 | 他の事務職の同僚も何人か残業していた。 確かに仕事は締めきりもあり忙しかった。 |
| バランス思考・プラン | 仕事は締めきりもあり忙しかったので、私に気をつかったのではないか。(50%) 信頼されているからこそ仕事が多いのだ。(65%) |
| 心の変化 | イライラ(40%)、あせり(30%)、悲しい(25%)、やる気(20%) |
認知行動療法は宿題(ホームワーク)が必須で、コラム表も自身でホームワークで記録していきます。
そして偏った否定的な認知(考え方)を変えていきます。
この否定的な認知は『患者さんのための資料』に以下の表が載っています。
うつ病でない方もたまに目に入ると良いと思うので表にして載せてしまいます。
| 認知のかたより(アンバランス) |
| 1)感情的きめつけ |
| 証拠もないのにネガティブな結論を引き出しやすいこと 「○○に違いない」 例:取引先から一日連絡がない → 「嫌われた」と思いこむ |
| 2)選択的注目 (こころの色眼鏡) |
| 良いこともたくさん起こっているのに,ささいなネガティブなことに注意が向く |
| 3)過度の一般化 |
| わずかな出来事から広範囲のことを結論づけてしまう 例:一つうまくいかないと、「自分は何一つ仕事が出来ない」と考える |
| 4)拡大解釈と過小評価 |
| 自分がしてしまった失敗など、都合の悪いことは大きく,反対に良くできていることは小さく考え る |
| 5)自己非難(個人化) |
| 本来自分に関係のない出来事まで自分のせいに考えたり、原因を必要以上に自分に関連づけ て、自分を責める |
| 6) “0か100か”思考(白黒思考・完璧主義) |
| 白黒つけないと気がすまない、非効率なまで完璧を求める 例:取引は成立したのに、期待の値段ではなかった、と自分を責める |
| 7)自分で実現してしまう予言 |
| 否定的な予測をして行動を制限し、その結果失敗する。そうして、否定的な予測をますます信じ込むという悪循環。 例:「誰も声をかけてくれないだろう」と引っこみ思案になって、ますます声をかけてもらえなくなる |
また、うつ病の認知行動療法というと「自動思考」「スキーマ」という言葉が出てきます。
自動思考は自然に出てくる考え方やイメージです。コラム表にも自動思考は書きます。
スキーマはいろんな分類の仕方があるようですが、
その人の根底にある中核的な信念
と考えてもらえればいいと思います。
(媒介信念という言葉が出てくるかもしれませんが、そこまで調べる必要はないと思います)
カウンセラー(鈴木)の印象ですが、認知行動療法は、
有効な方にはとても効果的
と思います。
ではそれはどんな方かというと、
思考優位と言いますか、理論的で合理的な方だと思います。
やはり認知(考え方)と行動に働きかけるので、これが正解となれば考え方を変更できる方。
結果・目的重視で効率的に考えて行動できる方は効果が出やすいと思います。
トレーニングというか、仕事のような感覚というか、そのように進められる方には向いているのではないでしょうか。
では、そうではない方は認知行動療法は向いていなくて、やらない方がいいのか?
というと、そういう訳でもありません。
うつ病になる時というのは多かれ少なかれ、何らかの考え方の偏りがあり、
「ねばならない」「べき」と考えて行き詰っていることが多いです。
千葉カウンセリングルームでも、型通りの認知行動療法ではなくても、
現在の考え方はどれほど現実的か、
現在の考え方のメリットは何か、反対にデメリットはありそうか、と検討していただきます。
また「ねばならない」「べき」は、
「~になれば確かにいいんだろうけど、そこまでならなくても、しょうがないかな」
のように柔らかくなっていただけると良いと思います。
長くなってしまいましたが、
上記の内容でうまくいく方は、認知行動療法で何とかなる方なのだと思います。
認知行動療法では足りない場合
カウンセラーの印象では、否定的なスキーマ(中核信念)が強くある場合、認知行動療法では足りないと思います。
スキーマは色々分類があるようですが、ひとまず2つ知っていれば良いと思います。
「私は出来が悪い(無力・弱い・出来損ないなど)」
と
「私は好かれない(魅力が無い・必要ではないなど)」です。
(文字で見るとインパクトが強い内容ですが…)
この否定的スキーマが強くあると、いくら認知と行動を触って何とかしようとしても、元に戻ってしまいます。
「考え方を変えるっていう理屈はわかったけど、でも~」となります。
一方で、認知行動療法も進化し続けていて、
現在は第三世代の認知行動療法といってマインドフルネスなども加わったりしています。
どんな悩みも認知行動療法一本で対応できるカウンセラーもいらっしゃると思います。
ただカウンセラー(鈴木)としては認知行動療法にこだわる理由はありません。
否定的なスキーマを扱う時には、
ゲシュタルト療法(といっても特別なことするのではなく大体は対話ですが)になることが多いです。
「べき」「ねばならない」は、
当時は生きていくのに必要だったけど、今はもう必要ない。
否定的なスキーマも、
〇〇さんから刷り込まれたけど、〇〇さんが勝手に言ってただけで、何の根拠もない。もう〇〇さんに振り回されない。
などのようになると、
考え方も柔らかくなったり、休みをとりやすくなって、
いろんなこと(仕事や人間関係や家事や育児や)が良い意味で「ほどほど」になったりします。
毎日が楽になって、うつ病から回復していきます。
またうつ病を何とかしようとすると、うまくいかなかったこと・できないことに焦点が当たりがちです。
それだけで終わってしまうと、さらに落ち込んでしまいます。
そうではなく、ソリューションフォーカストアプローチで、
問題が解決したらどうなっているか、
(べき・ねばならないではなく)本当はどうなりたいのか、
過去にうまくいっていた時はあったか、
あったならば、今とは何が違うのか、
過去の成功で今に活かそうなことは何か、
活かせたらどのような変化がありそうか、
などのように進むこともあります。
自分の中の既にある解決(過去の成功例)を元に現在・未来の解決像を作っていきますので、
前向きな気持ちで、一歩ずつ階段を上ることができます。
カウンセラーの助言が多くなるかもしれません
カウンセラー(鈴木)としては、
なるべくカウンセラーが結果を予測したり、〇〇しましょう、のように伝えるのは避けるように意識しています。
というのも、何事もやってみないと分からないからです。
ある人には効果があることも、別の人には逆効果だったりもします。
ですが、うつ病の方には提案・助言が増えることがあります。
というのも、うつ病の時は、何でもマイナスに考えてしまいます。
ですので、
大きな決断はしないようにしましょう、
と医師に言われた方もいらっしゃると思います。
離婚や転職・退職だけでなく、先延ばしにできる決断は、先延ばしで良いと思います。
うつ病の状態ですと、自分はうつ病で今は普段のような判断ができない、と自身を俯瞰することが難しいこともあります。
ですので、相談者に答えを見出してもらうのではなく、
カウンセラー(鈴木)が「今は~しましょう」と言うことが、多くなるかもしれません。
ご家族の方へ
うつ病になると収入や家事・育児にも影響が出ます。
ご本人はもちろん苦しいですが、ご家族も苦しくなります。
日本に住んでいると、うつ病の方を励ましてはいけない、と聞きます。
うつ病に限りませんが、世間一般の普通と比べたり、正論を伝えることの効果はないでしょう。
ですが、睡眠・食欲が戻り、生活リズムが整って、意欲もある程度出てきたら、
行動を増やす段階になります。
この段階では、周囲の方々はある程度は背中を押しても良いと思います。
(不登校やひきこもりと同じように)
背中の押し方も悩むところですが、
がんばろう、というよりも、気楽にいこう、という感じでしょうか。
背中の押し方も、ご本人が
少し押してほしいと思っているのか、それとも不要(やめてほしい)と思っているのか、
なんと言ってもらいたいと思っているのか、
によります。
ただ「べき」「ねばらない」で頑張ってうつ病になった方に、
「べき」「ねばならない」と背中を押すのは、
これまでの繰り返しになってしまうので避けたいところです。
またご本人がなかなか改善しないと、周囲の方も苦しいです。
いろいろとやり尽くして、それでもうつ病が改善する見込みが持てなくなると、不安や悲しみだけでなく、虚しさや怒りも感じます。
勘弁してよ、いい加減にしろ、甘えるな、と言いたくなります。
かといって、本人にぶつけてうつ病が悪化されても…となります。
ご家族が苦しくなるのも当然です。
そのような時は、(うつ病に限りませんが)自助グループやカウンセリングを利用されるのも選択肢と思います。
最後に
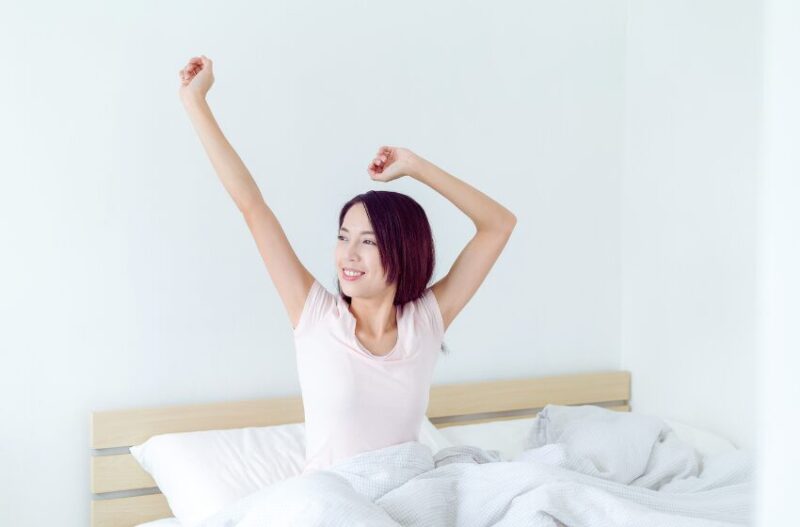
(繰り返しのセリフで申し訳ありませんが)
うつ病になったということは、これまでの考え方・生き方では行き詰った、ということなのでしょう。
これは典型的なうつ病も、そうではないうつ病も同様と思います。
休まず(休めず)働いて力尽きるようにうつ病になった方も、
上司に傷つけられたと主張して休職した(正式な診断名ではありませんが)未熟型うつ病の方も、
現状のやり方では越えられない壁に直面している、という点では同じです。
(うつ病に限りませんが)自分を守るためにうつ病になっている、という考え方もできます。
うつ病になられたら、一度医療機関にかかって、薬が出たら飲んで、十分に休んでいただきたいです。
うつ病と診断が出ることで周囲が配慮してくれることもありますし、休養で気分が上向くことでマイナスに考える悪循環を抜け出せることもあります。
ですが薬を飲んで休んだだけでは、これまでの考え方・生き方は変わりません。
この部分が同じままで、環境も変わらないのであれば、同じ繰り返しになってしまいます。
(実際に復職後に再度休職する方は珍しくありません)
休んでも・薬を飲んでも、また同じになってしまうかも、と思われる方は、
(当相談室でなくても)心理的な支援を受けてみる価値があると思います。
特に否定的なスキーマがあり、いろいろな面で日々が苦しい方には、生き方を検討する機会なのかもしれません。
なお、受診されている方は、カウンセリングを受ける際には医師の許可をいただいてください。
カウンセリングはある程度エネルギーが必要です。
うつ病の急性期にはカウンセリングよりも、休養が第一優先となります。
